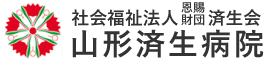リハビリテーション部/言語聴覚部門
言語聴覚部門
私たち言語聴覚士は、病気や事故によりコミュニケーション能力や食べる機能に障がいをもった方々へ、言語聴覚療法(言葉のリハビリ)、摂食機能療法(飲み込みのリハビリ)を行います。
私たちはふだん、言葉によってものを考え、意志を伝えています。また食べることは毎日3食繰り返され、日々の生活に大きく関わっています。どちらも生活の質に直結する大切なことです。これらに障がいをきたした方々やご家族を支援いたします。
Q:言語聴覚療法の対象は?
脳血管疾患(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)、脳腫瘍、神経筋疾患、肺炎、手術等によりコミュニケーション障がいや摂食嚥下障がい(飲み込みの障がい)、高次脳機能障がい(記憶障がい、注意障がい等)をきたした方々が対象となります。また、子どもの言葉の遅れや構音障がい等の訓練も行います。
Q:言語聴覚士は何人?
16名の言語聴覚士が、急性期チーム、回復期チームの2つに分かれて言語聴覚療法と摂食機能療法を実施します。
Q:言語聴覚療法はどんなことをするの?
言語聴覚療法
コミュニケーション障がいとは意図することが正確に相手に伝わらず、スムーズなコミュニケーションが難しくなることを言い、大きく失語症と構音障がいの2つに分けられます。
失語症は「相手が話す言葉の意味がわからない」「言葉が出てこない」「思った言葉と違う言葉を言ってしまう」「文字が読めない」「字が書けない」など聴く・話す・読む・書くの言語面が障がいされます。これらの症状に対して、絵カードや文字カードを用いて理解や発話を促し、更に読む練習や書く練習を行います。
構音障がいとは、「呂律が回らない」「発音が悪くなる」障がいです。発音に関わる器官(唇、頬、舌、のど等)の機能回復と、発音練習を行います。
ベッドサイドや言語療法室での個人訓練に加えて、集団訓練を行うこともあります。これはコミュ二ケーションの実用性を高めるだけでなく、様々な患者さんと接することで自分の障がいに対する理解をより深めることができます。

失語症訓練

構音訓練
摂食機能療法
摂食嚥下(えんげ)障がいとは食べる機能の障害です。うまく噛めない、飲み込めない、むせてしまうなど症状は様々です。安全に食事ができるよう、評価を行い、食べ物を使わない訓練と食べ物を使った訓練を行います。また、退院された後も継続して安全な食事を続けてもらうために、家族指導にも力を入れています。嚥下内視鏡検査や嚥下造影検査も取り入れておりますので、摂食嚥下障がいの診断がより正確に客観的に行えます。
また歯科衛生士と共に口腔内視診や専門的口腔ケアの介入も行い、合併症予防や食べられる口作りに努めています。

完全側臥位での摂食嚥下訓練

ニューロトリートを使用した訓練

言語聴覚士