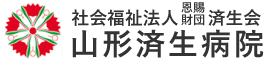健康コラム
#7 脂肪肝(しぼうかん)の最近の話題
脂肪肝の歴史
健康診断で肝機能異常を指摘され、「脂肪肝」と診断されたという人は多いと思います。脂肪肝は肝細胞に中性脂肪が蓄積された状態のことです。以前は脂肪肝の主な原因はお酒が原因と思われていましたが、1980年にアメリカの医師がお酒を飲まないにも関わらず肝臓の線維化が進行する脂肪肝の20例を報告し、「非アルコール性脂肪肝炎(nonalcoholic steatohepatitis : NASH)」の疾患概念を提唱しました。その後、1986年に病態進展に飲酒が関与しない脂肪肝を総称して「非アルコール性脂肪性肝疾患(nonalcoholic fatty liver disease:NAFLD)」とする概念が提唱されました。しかしながら当時はC型肝炎やB型肝炎が重大な問題だったこともあり、あまり話題になりませんでした。その後、1998年のアメリカの学会で、非アルコール性脂肪肝炎は肝硬変の重要な原因であると認識されるようになってから世界的に注目されるようになりました。
NAFLDからMAFLD、そしてMASLDへ
NAFLDの研究が進むにつれて、その発生や進行には、肥満、糖尿病、高脂血症、高血圧などが深くかかわっていることがわかってきました。そのため、2020年にはこれらの心代謝系危険因子を診断基準に含む新しい疾患概念としてMAFLD(metabolic dysfunction associated fatty liver disease)が提唱されました。しかしながら、MAFLDのFのfattyが肥満体形を揶揄する表現との意見もあり、数年後にMASLD(metabolic dysfunction associated steatotic liver disease)に名称が変更されました。同時に診断基準も一部変更されています。このように紆余曲折はありましたが、最新の表記はMASLD(読み方はマッスルディー)に落ち着いています。そして、このMASLDに該当して、かつ肝炎が生じている場合は、MASH(マッシュ、従来のNASH)と呼ぶようになりました。
MASLD(マッスルディー)について
MASLDは、画像検査で脂肪肝があり、アルコール摂取量男性30g/日、女性20g/日未満(アルコール20gはビール500ml、日本酒1合程度に相当)で、肥満・血糖・血圧・中性脂肪・HDLコレステロール値の基準を満たす患者さんが該当します。本邦では2,000万人以上いると推定されており、その中から将来的に肝硬変や肝臓がんまで進展する患者さんがいることになります。また、代謝異常や高血圧を合併することから、脳心血管疾患の発症や、肝がん以外の臓器からの発がんも上昇することが報告されています。これらのことから早期にMASLDと診断することで、脳心血管疾患の予防や肝がん以外のがんの早期発見が出来る可能性があります。
「ALT>30」でかかりつけ医受診を(奈良宣言2023より)
肝臓はある程度障害されても働き続けることができるため、病気になっても症状が出にくく、「沈黙の臓器」とも呼ばれています。また、MASLDを含む脂肪性肝疾患が増加している現在では早期診断・早期治療が重要になります。そこで日本肝臓学会は、2023年6月に奈良で開催された日本肝臓学会総会において、血液検査のALT値を指標として肝疾患の早期発見・早期治療を目指す、「奈良宣言2023」を発表しました。一般的に広く測定されているALT値を指標とするのが分かりやすいことから、「ALT>30」であった場合は、かかりつけ医にまず相談することを呼びかけています。ALT値が30を超えていたら、背後に「慢性肝臓病」が隠れている可能性があります。かかりつけ医の診察を受け、必要に応じて専門医を紹介受診し、かかりつけ医と専門医の連携により肝疾患の早期発見・早期治療を行うことが大切です。
FIB-4インデックスについて
肝臓病の進行度は肝臓の線維化(どれくらい肝臓が硬いか)の度合いと言えます。FIB-4 インデックスは血液生化学的検査データ(ALT、AST、血小板数)を用いたスコアリングシステムで、肝線維化の程度を確認できます。インターネットでFIB-4インデックスと検索すると計算式が表記されているサイトがあり、それに自分の年齢とデータを入力すると簡単に数値がわかります。FIB-4インデックスが1.30以上で肝臓の線維化が進行している可能性がありますので詳しい検査を受けることをお勧めします。年齢などで偽陽性になる場合もありますので、数値の解釈についてはかかりつけ医に御相談ください。
MASLDの治療
MASLDは患者数が多いことから世界中の製薬メーカーが新規治療薬の開発にしのぎを削っていましたが、今年の3月にアメリカでレスメスチロムという甲状腺ホルモン受容体β作動薬がMASHに対する有効性が認められて初めて承認されました。しかしながら、この薬は日本で治験が行われていないことや、推定薬価が年間700万円を超えること、MASH消失率が約30%に留まることから、日本での発売は不透明な状況であまり期待できません。従いまして、現在のMASLDの治療としては食事療法、運動療法が主体となります。体重の7%程度の減量で脂肪肝や炎症が改善することが報告されています。また、合併する代謝疾患や高血圧の治療がそのままMASLDの改善につながりますので、かかりつけ医と相談しながら、一人一人にあった治療を受けるのがベストです。
最後に
脂肪肝も放置すると知らないうちに進行する場合があります。血液検査でALTが30を超えていれば、是非かかりつけ医に相談してください。
引用文献
1.米田正人, 他. 〈総説〉脂肪性肝疾患(Steatotic liver disease : SLD)のパラダイムシフト:NAFLDからMASLDへ 肝臓 2024 ; 65 : 420-432
2.奈良宣言特設サイト https://www.jsh.or.jp/medical/nara_sengen/
3.肝臓検査.com https://kanzo-kensa.com/examination/calc/
松尾 拓(まつお たく)
【現 職】
消化器内科 内科統括診療部長
【資 格】
日本内科学会〔総合内科専門医・認定内科医・指導医〕
日本消化器病学会〔消化器病専門医・指導医〕
日本消化器内視鏡学会〔消化器内視鏡専門医・指導医〕
日本肝臓学会〔肝臓専門医〕
消化器内科についてはこちら
※ 所属・役職・資格等は公開当時のものです。異動・退職等により変わる場合もありますので、ご了承ください。
掲載日:2025年01月14日